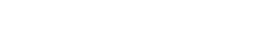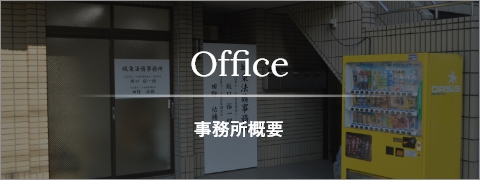ホーム > 業務案内 > 売買・贈与・抵当権抹消
Purchase 売買・贈与・抵当権抹消
売買の登記について
ここでは、不動産会社が仲介して中古住宅を売買する場合の手続きの流れをご説明します。

1.売買契約の締結
話がまとまれば、売買契約書を作成し契約を結びます。
契約と同時に、売買代金の10%から20%程度の金額を「手付け金」として支払います。
2.売り主・買い主の準備
売り主は、隣接地の所有者に立ち会ってもらって、土地の境界を確認します。境界が不明な場合は、土地家屋調査士に境界確定作業を依頼します。買い主が、金融機関から融資を受けて売買代金を用意する場合は、早めに融資の申し込みをします。
3.司法書士の準備
依頼を受けた司法書士は、登記に必要な書類を作成して準備をします。
4.不動産決済
決められた日時に、売り主・買い主・不動産会社担当者・融資を行う金融機関の担当者、それに司法書士が一同に会します。その場で、司法書士が売り主・買い主・融資を行う金融機関の三者から必要な書類を預かり、準備した「登記原因証明情報」や「委任状」といった必要書類に、当事者の署名押印をしていただきます。
司法書士は、すべての書類が整ったことを確認した後、金融機関に対して融資の実行と、買い主に対して売買代金残金の支払いをするよう促します。代金の支払いを確認して取引を終了します。
5.登記申請書の提出
司法書士は預かった書類を取りまとめて、登記所へ提出します。
6.登記の完了
登記完了後に発行される「登記完了証」「登記識別情報」「登記事項証明書」等をひとまとめにファイリングし、「不動産登記権利情報」として買い主にお渡しします。
贈与と相続の比較
「生きている間に息子に不動産を贈与した方が得ですか?それとも死亡してからの方がいいですか?」とよく聞かれますが、一概にはお答えできません。
あなたのご家族の状況や実情に合わせて、検討していただく必要があります。「贈与」と「相続」の特色を簡単な表にしております。

※横にスクロールしてご覧ください。
| 贈与 | 相続 | |
|---|---|---|
| 移転の時期 | 生前中に行う | 死後に行う |
| 渡す相手 (承継者) |
誰でもよい | 法定相続人に限る (遺贈なら誰でもよい) |
| 贈与税 | 暦年課税:年間110万円まで非課税 相続時精算課税制度:2,500万円まで非課税 |
– |
| 相続税 | – | 基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)までなら非課税 |
| 登録免許税 (登録時の税金) |
不動産評価額×2% | 不動産評価額×0.4% |
| 不動産取得税 | 宅地:不動産評価額×1/2×3% (時限規定あり) 居宅:不動産評価額×3% |
非課税 |
| 将来の相続税対策としての贈与 | 暦年課税制度:有効な相続税対策になる 相続時精算課税制度:相続税対策とはならない |
– |
| 農地の所有権移転 | 農地法所定の許可が必要 (農業を営んでいない者は、農地として取得することは不可能) |
農地法許可は不要 (農業を営んでいなくても農地の取得は可能) |
| 他の法定相続人 (例:兄弟姉妹等)の同意 |
不要 | 遺言がない場合は、法定相続人間の遺産分割協議が必要 |
不動産の贈与登記
贈与の特色
贈与は、ご本人が生存中、どなたに対しても行うことができます。このため、自分の意思で、自分の財産を、自分が思った人に承継させることが可能です。
ただし、贈与税や不動産取得税が課税されることもありますので、十分な検討が必要です。
夫婦間の居住用財産の贈与
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与が行われたとき、基礎控除110万円の他に最高2,000万円(合計で2,110万円)まで配偶者控除が受けられ、贈与税が非課税になる制度があります。
※登録免許税・不動産取得税は課税されます。
相続時精算課税制度
60歳以上の人が、20歳以上の子または孫に贈与する場合、2,500万円までなら贈与税は課税されず、贈与された財産は贈与した人が死亡したときに相続財産に加算し精算する制度を相続時精算課税制度といいます。
※住宅取得資金等の贈与は1,000万円加算されます。
抵当権の抹消
抵当権とは、金融機関が住宅ローンを貸す際、万が一お金が回収できない場合のため、担保として不動産を確保しておくことです。
住宅ローンを払い終われば当然抵当権はなくなるのですが、お金を借りていた金融機関が不動産登記簿謄本から消してくれるわけではありません。もし、抵当権がついたままだと、登記簿上はローンをまだ返済していないとみなされ、いろんなデメリットがあるため、住宅ローンの返済が終了したら、抵当権抹消登記が必要です。
お手続きの流れ
1.メールまたはお電話でお問い合わせ
2.費用の概算と必要書類のご連絡
売り主は、隣接地の所有者に立ち会ってもらって、土地の境界を確認します。境界が不明な場合は、土地家屋調査士に境界確定作業を依頼します。買い主が、金融機関から融資を受けて売買代金を用意する場合は、早めに融資の申し込みをします。
3.事務所への必要書類の郵送
必要書類をご返送ください。郵送料はお客様ご負担となります。
4.費用のご請求、お振り込み
届いた書類に基づき費用を請求させていただきますので、指定の口座へお振り込みください。
5.登記申請
入金確認後、登記を申請します。
6.登記完了後ご郵送
2週間から3週間後には、登記完了書類一式を郵送いたします。
Contact お問い合わせ
営業時間 9:00~18:00/定休日 土曜・日曜・祝日
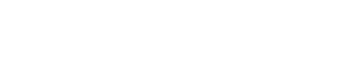
24時間受付中!